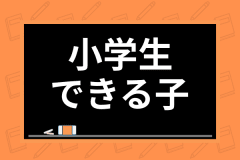小学生の勉強を習慣化する方法は?低学年からの勉強環境作り・親の接し方まで解説!
更新
小学生のうちから勉強を習慣化させることが大切とわかってはいるものの、 「どのように取り組めばいいのかわからない」 という方も多いでしょう。
そこで今回は、小学生の勉強を習慣化させるためにはどうすればいいのか、詳しく解説していきます。
低学年のうちから確固たる勉強習慣を身に付けることは将来的に最大のメリットになるでしょう。
小学生に学習を習慣化させるには、メンタルを重視してあげることが大切です。すぐに実践できる習慣作りの方法も詳しくご紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
勉強を習慣化する方法についてざっくり説明すると
- まずは実力よりも低い難易度から始める
- 徐々に習慣づけるよう、時間を大切にする
- 始めのうちは特にメンタルを重視する
小学生の勉強習慣はどうすれば作れる?

「うちの子、家じゃ全然勉強しない」など、頭を抱えている親も多いのではないでしょうか。
しかし、小学生に「勉強をしなさい」と漠然といっても、まだ自主的に管理して取り組むことは難しいです。
では、どうすれば始めの一歩を踏み出せるのか、お話していきましょう。学年問わず、自宅学習をする習慣作りをはじめる方法をご紹介するので、参考にしてくださいね。
はじめは短い時間から
「さあやるぞ!」と親が気合を入れても、子供にはまだ勉強スイッチが入っていないことがほとんどです。「遊びたい」「YouTubeやTVが見たい」などといった自分がしたいことへの欲求が強いでしょう。
そのため、たった1時間の勉強時間でさえ子供にとっては苦痛の時間です。苦痛の時間が長ければ長いほど、「勉強=嫌なこと」とインプットされてしまい、余計に勉強スイッチが作動しません。
まずは、宿題など簡単なものを20分程度から始めることが大切です。そして、20分勉強をやったら必ず褒めてあげてください。
このとき、勉強の良し悪しは気にしてはいけません。「勉強をしたこと」をほめてあげましょう。
また、「勉強をしたらおやつ食べていいよ」などといったようなご褒美制を取り入れるのは絶対に避けてください。その理由については以下で解説します。
ご褒美は逆効果?
子供が何かをできたご褒美として、プレゼントをあげたことがあるという方も多いではないでしょうか。
サプライズでご褒美としてではなくプレゼントをあげるのであればいいですが、 「勉強したらお菓子食べていいよ」 「成績が上がったらお小遣いをあげる」 などといった、ご褒美制はかえって本人のやる気を奪ってしまう可能性があります。
本来、子供のやる気というのは勉強への意欲によって学習をするという行動に出るものです。この時点では、自分の欲求(内発的動機)によって勉強をしています。
しかし、ここへ「ご褒美」という報酬が与えられることによって「ご褒美をもらうためにやる」という意欲(外発的動機)に変わってしまいます。これをアンダーマイニング効果といいます。
内発的欲求には損得感情はありませんが、外発的動機には損得感情が生まれやすく、もともと「嫌なもの」と認識している勉強とご褒美を、天秤にかけるようになるのです。
やる気に関してご褒美によるモチベーションが勉強に勝ち続ければまだいいですが、「別にご褒美はなくてもいいや」と思ってしまった場合、その子は勉強に取り組むことが難しくなるでしょう。
ご褒美は、始めのうちは効果を感じられることもありますが、長期的に継続するのは難しいので勉強習慣をつけるという面では避けましょう。
アンダーマイニング効果についてより詳しく知りたい方は、以下の論文をご確認ください。
勉強を好きになるのが一番
内発的欲求を育てていき「勉強を好きになる」ことが、勉強習慣作りの一番の方法といえます。
しかしこれはあくまで理想的な話であり、これから勉強習慣作りを始める子供にとっては無理な話です。「勉強しなくちゃいけないのか」とうつうつとした気持ちになる子が圧倒的に多いでしょう。
まず、勉強を始めるには勉強への嫌い・イヤだという負の感情を持たせないことが大切です。一度勉強を嫌いなものと感じてしまうと、今日は勉強ができても明日はできないなど習慣作りが難しくなります。
特に高学年であれば、勉強に抵抗を感じている子も多いでしょう。
すでに勉強に負の感情を持ってしまっている場合は、勉強を好きになることよりも、これ以上嫌いにさせない、そして勉強に対する抵抗感をなくすことで、勉強の習慣作りがスムーズになります。
低学年の頃の習慣が大事?
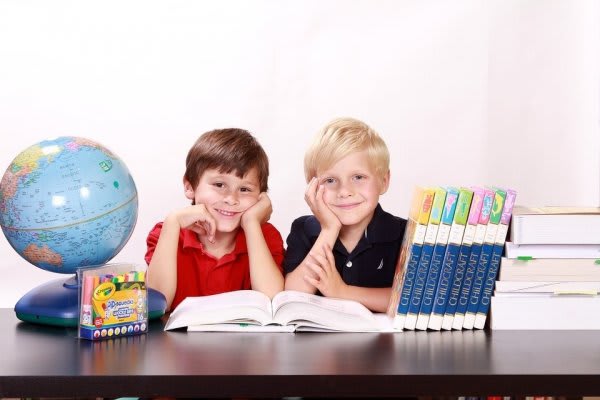
小学生のうちから勉強の習慣作りが大切と言われていますが、なかでも低学年から勉強習慣の構築が大切だとされています。
その理由として主に3つのポイントについて紹介していきます。
小学生の勉強時間からの視点
小学生の理想的な家庭学習時間は、「学年×15分」だと耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。1年生であれば15分、5年生であれば80分が理想的な時間になります。
また、ベネッセの2015年に実施された第5回学習基本調査(家庭での学習時間)によれば、小学生の平均勉強時間は約95分となっています。これは、6年生の理想的な勉強時間に相当します。
しかし、今まで「勉強をする」という習慣が身についていない子供にとって、いきなり90分もの勉強をしなさいといっても苦痛に感じてしまう子も多いでしょう。
あまり勉強時間にこだわる必要はありませんが、理想とする家庭学習時間が短い低学年から勉強習慣を身につけた方が、本人への負担も少なく勉強というハードルを越えやすくなるのでおすすめです。
勉強の難易度が低く挫折しにくい
低学年の頃であれば、学習の遅れを感じにくいため勉強への入り口としては入りやすいといえるでしょう。
また、勉強に対して苦手意識も低く、わからないところも解決しやすいため、低学年から勉強をはじめた方が挫折しにくいと言えます。
高学年になって学校での勉強についていけないとなると、時には学年を下げて基礎からやり直さなくてはいけないため、モチベーションを保つには難しいでしょう。
勉強に対する好奇心が強い
学年が上がるにつれて、授業へ参加する姿勢が悪くなる傾向があります。授業参観などを見比べるとわかりやすいのですが、低学年の方が挙手をする子や積極的に発言をする子が多いというのが事実です。
また、学年が上がるにつれて 「授業で発言するのが恥ずかしい」 「まじめに授業を受けるのがかっこ悪い」 などと、少し斜めに構えてしまう子もいます。これも成長の一つではあるものの、ここから勉強を習慣づけようとすると大変だというのは想像できますね。
そのため、低学年のうちから勉強の習慣をつけることが大切なのです。
勉強習慣作りの具体的な方法

では、どのようにすると勉強を習慣づけすることができるのでしょうか。
理想的な勉強習慣作りの方法としては、普段の生活ルーティーンの中に勉強を確立させ、無理なく継続できる方法が理想的です。
そこで、勉強を生活ルーティーンに取り入れるポイントについていくつか解説していきましょう。
勉強場所と時間を固定する
ポイントの1つ目は、勉強の場所と時間の固定です。
自分の机や今のテーブルでやったり、ダイニングでやったりと自分の気分次第で勉強をする場所を変えるのではなく、勉強する場所はココ!と決めてしまいましょう。
勉強場所を変えることで気分を変えることはできるものの、習慣としてはつきにくいです。
また、毎日違う時間に学習をするのではなく、決まった時間を勉強時間とすることで、生活に取り入れやすくなります。
部屋で勉強させない?
小学生になると、自分の部屋を持っているという子も多いのではないでしょうか。自分の部屋の机で勉強をするというシステムは、どの家庭でも見かけるものです。
しかし、勉強の習慣が根付いていない子供にとって、自分の部屋で勉強をするということは、とてもハードルが高いものになります。
部屋には子供の気をひくものが多いですし、独りで勉強をすると集中力が続きにくくなります。まずは、ダイニングテーブルなど親の目が届く場所で勉強を始めましょう。
そのためにはテーブルは常にきれいな状態を心がけましょう。また、親自身がテーブルで作業をするという習慣を見せるのもおすすめです。
その姿を見て、自発的に勉強をし始めることもあります。
文房具にこだわる
大人でも、形から入ることでモチベーションが上がる人は多いですよね。
同じように、子供のモチベーションを上げるアイテムとして文房具があります。好きな文房具をそろえてあげることで、やる気がアップする子も多いです。
好きなキャラクターや、お気に入りのノート・筆記用具を揃えることで、その「文房具を早く使いたい!」と勉強に積極的に向かうようになることもあります。
家計として出費がいたいところですが、勉強を始める入り口として子供が気に入ったものをできるだけ揃えてあげましょう。
達成度がわかる表を作る
勉強をしたことへの達成感は、すぐには感じにくいものです。
特に、小学生には勉強をしたことによってどうなったのか、自分はどう変化したのかなどといった、勉強をすることによる自分へのメリットといったものがよく理解できていません。
そのため、始めは勉強を続けられたとしても、勉強をすることへの達成感が得られないため、次第にモチベーションを下げてしまう子が多いです。
そこで、達成感がわかる表などをつくることをおすすめします。
どこかのお店でポイントカードを利用したことがある方であれば、ポイントが貯まっていくことに達成感を感じた経験がある方も多いのではないでしょうか。
子供も同様に、自分が頑張ったものが目に見えることで、続けようとやる気を出す子も多いです。
たとえば、100均などで手帳を購入し勉強をした日にシールを張るなど、ささいなもので構いません。「目に見える」ことが重要です。
文房具と同じようにシールや手帳、表などは好きなものを選ばせてあげてくださいね。
ここで大切なのは、「勉強をした」という行為への達成感を示すことです。勉強の中身を評価し示してしまうと、やる気を失くしてしまう子も多いため気をつけましょう。
一番大事なのは褒めること
勉強が嫌い・苦手という意識を持っている子は多いです。
そういったネガティブな思考をポジティブへ変換してあげることで、学習への抵抗もなくなり、積極的に取り組めるようになります。
ポジティブへ変換する方法として、成績が上がる、授業がわかるといったものがありますが、それらは日常的に変換できる方法ではありません。家庭では、日常的に少しずつポジティブへ変換することが大切です。
そのためには、「褒める」ということはとても重要なポイントになります。
勉強を教えていて、理解できるようになってきたなと思ったら「できるようになってきたね」など、声をかけてあげてください。ただ丸つけをするだけではなく、できたことを褒めるよう意識しましょう。
特に、わからないところを聞かれて「そんなこともわからないの?」というのではなく、「解決しようとして偉い!」などといったようにポジティブな反応をしてあげるようにしてください。
塾や通信教育で勉強習慣はつく?
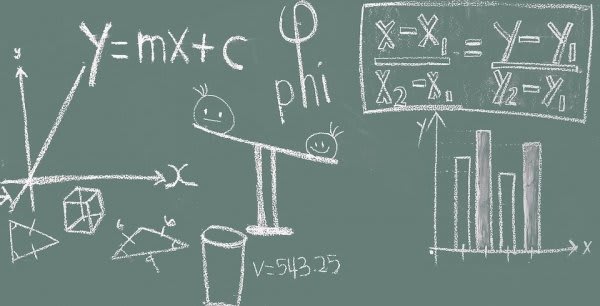
家庭での勉強方法として、通信教育や塾の利用を検討している方も多いのではないでしょうか。
塾に通っているからといって、勉強習慣が身につくかといえば、そのようなことはありません。しかし、通信教育であれば活用方法によっては勉強習慣が身につくこともあります。
通信教育や塾で勉強習慣は身につくのか、解説していきましょう。
塾に通うといい?
先述したように、塾に通っているからといって、勉強習慣が身につくわけではありません。
塾は、通う曜日が決められているため、毎日の習慣になりにくいといえるでしょう。
本人が行きたいと希望したのであれば検討するべきですが、勉強の習慣作りとしてはおすすめできません。
もともと勉強に対してネガティブな感情を持っている子供にとって、強制的に通わせられる塾は苦痛な時間であり、より抵抗を感じる材料になりかねないでしょう。
中学受験を検討していないのであれば、まずは、学校の教材をしっかりとやることが大切です。
通信教育で自主性を身に付ける
塾に通わせることは、学校外での学習時間を増やすことにはなりますが、「自発的な学習」ができるかがポイントとなるでしょう。
料金的な側面から見ても気軽に始めるには、通信教育をおすすめします。
塾と比べると、通信教育はサポート力に欠ける部分がありますが、学校の予習・復習をしたい、わかりやすい説明が欲しいなどといった希望を叶えてくれます。
そして何よりも、毎日の自宅学習で利用できるという点は大きいです。毎日の勉強習慣を身につけるためには自宅でできることが大切です。
小学生におすすめの通信教育は以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
小学生の勉強を習慣化する方法についてまとめ
勉強の習慣化させる方法についてまとめ
- 「勉強をしよう」という内発的欲求を育てることが大切
- ご褒美制は絶対とらない
- 学年問わず少ない時間から始める
- とにかく褒めて勉強への苦手意識を改善する
小学生は好奇心が強く、思うように勉強習慣が定着しないということはよくあります。
そういったときは、少ない時間から子供と一緒にテーブルに向かうなど、なるべく寄り添うようにしましょう。
小学生のうちから勉強の習慣作りをするためには、親の協力は必須です。それが親子のコミュニケーションにもつながります。
ぜひこの記事を参考に、子供が勉強に取り組めるよう、学習環境づくりをしてみてくださいね。